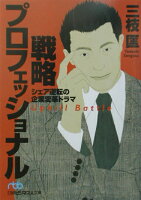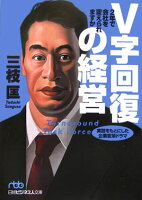未経験にも分かりやすく解説!コンサルタントの仕事内容とは

コンサルタントとはどのような仕事をしているかご存じでしょうか?
事業会社でコンサルタントと一緒に働いたことがある方や、コーポレートや企画系の部署にいて社内横断プロジェクトなどを経験したことがある方なら、イメージがわくかもしれません。以前の僕のように、営業しかやったことが無いような方にも分かるように、コンサルタントとはどのような仕事なのかを詳しく解説していきます。
昨今、巷では「○○コンサルタント」という名称の職種がかなり多く登場しておりますが、ここでは「戦略コンサルタント」や「経営コンサルタント」と呼ばれて企業に対するコンサルティングを行う、最も一般的なコンサルタントについて書いていきます。
コンサルタントの仕事は経営課題の解決
コンサルティングの仕事内容を簡単に言うと、“経営課題を抱える様々なクライアントに対して、問題を解決するための提言・助言や実行に向けたサポートを行う仕事”です。
Wikipediaには以下のように記載されていました。
コンサルティング (consulting) とは、企業(まれに行政など公共機関)などの役員(特に経営者が多い)に対して解決策を示し、その発展を助ける業務のこと。または、その業務を行うこと。対応する日本語はない。社会的に、コンサルティング会社は、特定の事業に特化した事業会社とは区別され、コンサルティングファームと呼ばれる。
Wikipedia 『コンサルティング』より
これを見てかなり幅広いと感じる方もいらっしゃるかと思いますが、コンサルの仕事は本当に多岐に渡ります。
例えば僕が所属している外資系コンサルティングファームでは以下のようなプロジェクトを受注しています。
- 通信会社における新規事業の企画・立案・立ち上げ支援
- 医療機器メーカーの 海外企業M&Aに伴うグローバル組織再編
- 自動車メーカーにおける海外進出戦略策定
- 不動産会社における人材マネジメント戦略の構築
- 保険会社の統合に伴う大規模システム構想策定
- 総合電機メーカーのシェアードサービス会社設立支援
上記はあくまでもプロジェクトのテーマですが、仕事やタスクの単位で見ると更に多種多様です。
例えば、クライアント企業の名刺を持って営業の人と一緒に現場を回ったり、ある調査をするために役所に偽名で電話して法律の解釈を確かめたり・・・自分が何屋なのか分からなくなることすらあります。
コンサルの仕事の90%はプロジェクトのデリバリー

コンサルティングの仕事は、ある特定のクライアントの経営課題に対して、毎回、“期間”と“予算”を決めてコンサルタントが解決にあたるプロジェクトの形態をとります。
クライアントが抱えている課題を解決するために、課題に対して適切な経験のあるコンサルタントが社内から選抜され、プロジェクトチームが結成されます。プロジェクトチームに配属されることを“アサイン”と呼び、コンサルタントは社内のいずれかのプロジェクトにアサインされて仕事をすることになります。
そのため、事業会社にあるような営業部や事業企画部といった固定的な組織は存在せず、プロジェクトごとに一緒に働くメンバーも上司すらも異なることが一般的です。プロジェクトが終了するとプロジェクトチームは解散となり、メンバーはまたそれぞれ別々のプロジェクトにアサインされます。
コンサルの仕事は、このようなプロジェクトに入ってデリバリーすること(人を動かすことや、実際に自分で作業などをしてプロジェクトを円滑に進めること)が大半となります。
もちろん、コンサルファーム全体として見るとプロジェクト以外の仕事もあるのですが、事業会社からコンサルに転職して暫くはプロジェクトくらいしかないと考えておいて良いです。
また、プロジェクトという仕事の進め方をしたことがない方だと、少しイメージがつきにくいでしょうし、そもそもプロジェクトという働き方が自分に合うのか判断しにくいと思います。
プロジェクト型であることのメリットは大きくは以下の3つ
- 期間が決まっているのでいつか終わりが来ること
- 人間関係などで悩むことが少ないこと
- プロジェクトの合間に長期休みを取りやすいこと
プロジェクト型のデメリットは大きくは以下3つ
- プロジェクト外での社内人脈が広がりにくい
- プロジェクト終了後にアベイラブルリスクがあること
- キャリア形成を自分でコントロールしにくいこと
それぞれ上記のようなことが挙げられます。ここは改めて別の記事で詳しく解説したいと思いますので、 それらを踏まえてプロジェクト型の働き方が合うかどうか考えていただけると良いと思います。
コンサルプロジェクトの流れは4ステップで説明できる

コンサルの仕事は医者の仕事と似ているとよく言われます。
仕事の流れは医者と似ていて、患者に症状を聞いて、必要な検査を行うことで病気の原因を突き止めて、適切な処置(時には外科手術が必要になることもあれば、投薬治療で様子を見ることも)を行う。必要に応じてリハビリで患者に寄り添い、快復に向かうようであれば経過観察を続け、そうでなければまた最初の診断からのサイクルを行うイメージです。
コンサルでは、主には以下の流れをとることが一般的です。
- ヒアリング等を踏まえた診断・仮説立案
- 各種分析を通じた仮説検証・課題特定
- 課題解決に向けた方針・戦略策定
- 実行サポート
ヒアリング等を踏まえた診断・仮説立案
このステップは営業・受注~プロジェクト開始くらいまでのイメージです。
営業をしている時期から、クライアントが困っていることやクライアント社内で起きている問題についてヒアリングを行うことで、そのクライアントが抱えている課題の仮説を立てます。
仮説を立てずに次のステップである分析から行ってしまうのは非常に危険で、多くのデータ・情報に埋もれてしまって、結局何が課題か分からなくなってしまうことや、絨毯爆撃を行って作業工数が足りなくなってしまうことに繋がります。
こうなってしまうと途中で軌道修正するのはなかなかしんどいです。
そのため、最初にクライアントの困っていることをある程度ヒアリングするのです。業界やクライアントのことを理解・把握しつつ、課題の仮説(+プロジェクトのゴールイメージ)を立てて、以降のステップではその仮説が正しいかどうかを検証しにいくという進め方をします。
事業会社からコンサルに転職した後の大きな壁として、この仮説を立てるステップは難しいと感じる人が多いです。情報がない状態で、仮説に仮説を重ねてストーリーとして組み立てていくことは慣れないうちは非常に時間がかかります。
コンサルの選考でよくある「ケース面接」で「フェルミ推定」という手法を使うのですが、そういった手法を活用することで仮説を立案できることもありますし、経営に関する知識や一般的な会社の仕組み全般を理解していないと仮説立案が難しいこともあります。
コンサルとして優秀な人は、この仮説の精度が非常に高いです。プロジェクトのキックオフの段階で、既に最終報告を聞いているかのようなストーリーが出来上がっていることもあるくらいです。
ただ、やはり仮説は仮説ですので、間違っていたからと言ってそれだけで大きく問題になることはありません。クライアントとのコミュニケーションや、検証を通じて仮説を修正していけば良いのです。
僕はよく一つのプロジェクトが終わった後に、プロジェクトの初期に作った仮説を振り返ることがあるのですが、初期仮説で考えていた内容とは全く異なる結果になっていたということもあります。
コンサルへの転職を目指す方は選考を受ける時点でもある程度の仮説思考力を見られますので、基礎的な仮説立案はできるようになっておくと良いでしょう。
各種分析を通じた仮説検証・課題特定
仮説を立てた後は、その仮説を検証するための分析を行い、課題を特定します。
コンサルの分析では定量的にも、定性的にも様々な分析を行いますが、定量的な分析であれば、既に収集されている様々なデータを活用して(もしくは新たにデータを集計して)、ExcelやSPSS、tableau等のツールで分析することが多いです。
扱うデータは様々です。事業戦略策定や市場調査のようなプロジェクトテーマであれば外部ソースや顧客に関するデータを活用します。逆に社内の課題解決を行うプロジェクトであれば従業員に関するデータや財務諸表・勘定科目などの内部データを活用します。
分析の切り口は、時間軸で過去から現在までの推移を分析することもあれば、現在の状態のみを様々な切り口から分析することもあります。
定性的な分析を行う際には、書籍・文献やインターネットを通じたデスクトップリサーチによる情報収集や、インタビュー・ヒアリングを行って得た情報をベースに行うことが多いです。
インタビュー・ヒアリングを行う場合は、対象者や順番、形式、質問項目などを設計するところから入ることが一般的です。また社内だけでなく、社外の専門家や競合企業にヒアリングするようなこともあります。
もちろんコンサルファームが独自に保有する知見・ナレッジを活用する場合もあります(当然、各社との守秘義務を守ることを大前提としています)。
ここで得た分析結果をもとに課題を特定します。
難しい課題は往々にして様々な課題が複雑に絡み合っているもので、真因を特定することから始めることも多いです。
ちなみに皆さんは「課題」と「問題」の違いをご存知でしょうか?
コンサルとして仕事をしていると、よく上記の違いについて議論する(もしくは上位者から下位者に対して指摘している)場面がよく見られます。
「課題」、「問題」と似たようなところで「事象」もありますので、コンサル転職を目指す方はこのあたりの違いについても抑えておくと良いでしょう。
課題解決に向けた方針・戦略策定
前のステップで特定した課題の解決に向けて、方針や戦略を策定します。
医者の仕事の流れで言えば、処置・治療の部分にあたり、病気を治すために外科手術をするのか、投薬で様子を見るのかといった具体的に行うことを決めていくステップとなります。
戦略や方針レベルでは、外部環境や前提条件を踏まえて複数のシナリオを用意することが一般的です。その上で各シナリオでとるべき具体的な施策について網羅的に洗い出していくことになります。
更に、それぞれの施策の実行にかかる費用や得られる効果の試算、メリット・デメリットの整理、実現可能性、効果が発現する時間軸・タイミングといった複数の観点から評価をして、施策の優先順位やロードマップ・スケジュールを策定していくという流れをとります。
ここで決まった戦略や方針、具体的な施策が、IR等で社外に発表されたり、ニュ
ースや新聞に取り上げられたりすると、やりがいにもつながります。少しミーハーな気もしますが、実際にニュース番組を見ていて自分の関与したプロジェクトについて報道されていると、いつもより真剣に見てしまうものです。
ちなみに、戦略といっても全社レベルの戦略もあれば、事業別、機能別(IT、財務・経理、人事等)等、様々な階層や単位のものがありますが、基本的な流れやそこで行う実際のタスクはどれも同じようなものになると理解していただくと良いかと思います。
よく新卒の方や、事業会社からコンサル転職を目指している方とお話している中で、「コンサルでどんな仕事をしてみたいのか?」と質問すると、「戦略系の案件に関わりたい」という返答を聞きます。
しかし、「戦略」とは特定の目的(上記で言えば企業の課題解決)を果たすために中長期的な視点と、複合的な思考で作り上げる計画であり、特定のテーマを指すものではありません。
そこを理解していただいた上で、自分のやりたいことは企業戦略なのか事業戦略なのか、あるいは競合との競争戦略なのか新市場への進出戦略なのか、特定の機能戦略なのか、といったことを考えておくのが良いでしょう。
実行サポート
このステップになってくると、結構プロジェクトテーマは絞られてきます。よくあるのは、システム開発や全社のトランスフォーメーションといった大規模なプロジェクトのPMOです。
PMOはProject Management Officeといって、クライアントのプロジェクトオーナーやリーダーの直下に横断チームとして設置する事務局です。言ってしまえば「何でも屋さん」です。
よくある仕事としてはプロジェクト全体のタスク・スケジュール管理と課題管理ですが、炎上プロジェクトになると、PMOも個別の検討テーマ・タスクをもって火消しに走るようなことも多いです。
他にもPMI(Post Merger Integration)といって、M&A後の統合支援に入ることもありますが、これも実行サポートの一例です。
実行サポートのフェーズになると、クライアントのプロジェクトチームも大人数になってきて、役員や部長層だけでなく、課長層や一般社員も関与してくる場合もあります。
実行サポートの難しさは何といっても、このプロジェクトの関与者が増える=利害関係者が増えることによる調整業務の発生です。
等級や階層の違い、所属する組織の違い(時には法人が違うことも)、社歴の違いなどによって、各自が抱えている思惑や大事にしている価値観が大きく異なり、利害が一致せずに調整に時間がかかることも多々あります。
事務局というと、単にスケジュール管理や雑務だけやっている人というイメージをお持ちになる方もいらっしゃるかもしれませんが、プロジェクト横断ですべてのテーマについて精通し、常に課題をウォッチし続けて、課題が出てきたらすぐに解決に向けて行動する、というのは実は意外と難しいものです。
新卒から事業会社に長くいる方だと、自分は調整業務が得意だとおっしゃる方も多いのですが、コンサルとしての調整業務は別物です。
なぜなら何年も同じ環境にいて、既に知っている人や関係構築できている人が何人もいる環境の中で行う調整業務とは異なり、社外の立場として調整業務を行うというのは、各関係者のレベル感や組織力学・人間関係も全くわからない中で、数カ月あるいは数週間でクライアントのキーマンを探し出して関係構築を行い、必要に応じて根回し等もしながら、複数部門の関係者と合意を取り付けていかなければならないからです。
そのため、コンサルには営業のようなコミュニケーション力も必要となります。分析や資料作成が好きでいくら地頭が良くても、人と関わるよりパソコンと向き合っていたいという方にとってはきつい職場かもしれません。
コンサルの仕事をより深く、具体的に理解するには本が一番

ここまでかなり詳しくコンサルタントの仕事を解説してきましたが、ご理解いただけたでしょうか?
何となくイメージは湧いたけど、具体的にどういうことをやるのかもう少しイメージを固めたい方は是非、以下のような本を読むことをおすすめします。
僕もコンサルファームへの転職を考えた時に以下のような書籍を読んでコンサルファームでの仕事のイメージを膨らませることで、さらにコンサルファームに転職したい気持ちが強くなったのを覚えています。
一番のおすすめは実体験を基に書かれた小説
戦略プロフェッショナル(三枝匡)
ミスミの元代表取締役・三枝匡氏の描いた小説で、新しい競争のルールを創り出し、市場シェアの大逆転を起こした36歳の変革リーダーである広川洋一を主人公として改革プロセスを具体的に描く、実話をもとにしたストーリー。
V字回復の経営(三枝匡)
こちらも三枝氏の描いた小説。太陽産業という架空の上場企業をどのように再建していくのかを、外部・内部それぞれの視点で描いたストーリー。
企業再生プロフェッショナル(アリックス・パートナーズ/西浦裕二)
企業再生に強みのあるアリックス・パートナーズが出した書籍で、企業再生プロフェッショナル(ターンアラウンド・スペシャリスト)として、経営の行き詰まった会社に乗り込み、実際に経営に参加して経営を中から立て直す様子を描いています。
コンサルマインドに焦点を当てた本は内定直前に読んで覚悟を決める
コンサルティングとは何か(堀 紘一)
戦略ファームであるBCGの会長 堀 紘一氏が描いた新書、BCGに在籍していた頃の話なども盛り込まれています。252ページとそれなりに分量はあるものの、難しい言葉も少なくとても読みやすいです。
プロフェッショナル原論(波頭亮)
こちらも同様に戦略ファームであるXEEDの社長 波頭亮氏の著書です。コンサルタントというより、プロフェッショナルとは何かという視点で書かれていますが、コンサルとして持つべきマインドが的確に書かれています。
体系的に理解しておきたい方には教科書系がおすすめ
この1冊で全て分かるコンサルティングの基本
各ファームの具体的なプロジェクト事例を紹介しながら、コンサルティングという仕事について書いた本です。実際のプロジェクト事例が書かれているため仕事のイメージがしやすいかもしれません。
上記の中でも特に小説系のものがやはり面白いです。主観的な目線から書かれているので、イメージを膨らませるにはぴったりです。
他にもオススメの本があれば、引き続きこのサイトでも紹介していきたいと思います。
-
前の記事
記事がありません
-
次の記事

コンサルの仕事はプロジェクトだけではない?コンサルにとって大事な3つの仕事