コンサルの仕事はプロジェクトだけではない?コンサルにとって大事な3つの仕事

以前、こちらの記事でも書いた通り、コンサルの仕事の大半はプロジェクトのデリバリーです。
デリバリーとは実際にプロジェクトを推進すること(具体的には、人を動かしたり、実際に自分で手を動かして円滑に進めること )です。
ただ、実はプロジェクトデリバリー以外にもコンサルの仕事はあります。今回はコンサルタントの仕事内容のうち、プロジェクト以外のものについて詳しく解説していきます。
ファームによっては関与することになる3つの仕事
コンサルタントのランク(等級・職位)によっては関与しない(関与させない)コンサルファームもありますが、プロジェクト以外の仕事は概ね以下の3つに集約されます。
・営業・マーケティング活動
・サービス開発・研究活動
・自社の組織運営活動
コンサルタントに対して上記の仕事をさせるか、させないは各コンサルファームの考え方や置かれている状況の違いによるところが大きいと感じます。もしかしたらファームの中でチームごとの違いもあるかもしれません。
まず上記3つの仕事をうまく進めていくには、コンサルプロジェクトとは違った思考や行動が求められます。
そのため、コンサルはとにかく多くのプロジェクトを経験することで思考力が高まり、コンサルとしての能力も高くなっていくのである、と考えるコンサルファームでは上記の仕事をスタッフレベルから関与させることはしないです。
逆に様々な経験をさせてコンサルとしての深みをつけさせることや、将来の期待役割として新たな仕事をとってくること(営業)を置いているところではスタッフのうちから上記の仕事に積極的に関与させることもあります。
また上記の仕事はルーティン業務の側面が強く、集約するとそれなりの工数になりますし、ちゃんとやろうとするとそれなりに工数のかかることです。
そのため小さいコンサルファームなどでは人手が足りず、やむを得ず上記の仕事にスタッフレベルのコンサルタントから関与させているというところもあります。
それでは具体的にどのような仕事なのかを詳しく見ていきます。
基本的にはPull型の営業・マーケティング活動

営業活動というと全く知らない会社に電話をかけたり、ビルにある各階のオフィスを上から下まで飛び込みで訪問したりといったイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、コンサル業界ではそういったPush型の営業は一般的ではありません。
そもそもコンサルのサービスは、「貴方の会社のここが問題です。ここをこう変えるべきです」といったことを指摘するようなものですので、いきなり電話をかけて(あるいは飛び込みで訪問して)そんなことを言われたら怪しいと思いませんか?
また基本的にはトップ営業なので、パートナーやディレクターと呼ばれる最上位クラスのコンサルタントが、会社の経営者などに対して営業を行うことが一般的です(ファームによってはマネジャークラスが中心となることや、独自の営業部隊がいるところもありますが)。
そのため、受注したい案件やプロジェクトテーマに関連するセミナー開催や執筆・寄稿といったマーケティング活動を行い、個別に問い合わせや引き合いをいただいたり、個別の相談を受けていく中で案件を受注する流れが多いのです。
営業に行った際には、クライアントが困っていることをヒアリングし、その困っていることを解決するためにはどのようなことをすれば良いかをプロジェクトとして提案します。同じようなテーマであってもその会社の置かれた状況や組織・体制やカルチャーなどを踏まえて、最適なアプローチをディスカッションしながら決めていくというイメージです。
マーケティング活動というと一般的には顧客の行動データを分析をしたり、広告などによるプロモーション戦略を考えたりといったB to C業界におけるマーケティングのイメージが強いかもしれませんが、上記のような理由からコンサルタントが直接マーケティング活動を行うのです。
ちなみに執筆活動は、業界本(インダストリーごとに特化したものもあれば、人事や会計など領域ごとに特化したものもあります)への寄稿、ウェブサイト・ニュースレター等の自社メディアを活用したもの、もしくはある特定のテーマを決めて本を書くようなこともあります。
セミナーや執筆活動は自分の名前を売ることにも繋がりますし、むしろ関与したいと考えるスタッフは多いと感じます。
将来の種まきとなるサービス開発・研究活動

サービス開発と言っても一般の事業会社のように、新しいビジネスモデルのものを作り出して、これまでと異なる価格モデルを決めて、といったような複雑なものではありません。
基本的にコンサルファームが売るのはコンサルティングサービス(プロジェクト)であり、どの程度の工数がかかるか(=何人のコンサルタントを、どのくらいの期間アサインするのか)によって金額が決まるビジネスモデルで、それ自体が変わることは少ないです。
昨今ではコンサルファームも様々な領域拡張を行っていて、コンサルティングサービス以外での収益化を模索しているところも多いですが、まだまだ上記のような一般的なコンサルティングサービスを売ることが多いです。
そのためコンサルファームで言うところのサービス開発とは、『これまでに似たようなプロジェクトは受注していたが、改めてサービスとして打ち出すようなもの(看板を掲げる)』もしくは『大学などの研究機関等で研究され概念として発表されたものを、新たにビジネスの世界に持ち込むようなもの』のどちらかになります。
既存のものをサービスとして改めて打ち出す
前者は言葉通りの意味で、例えば組織・人事コンサルティングサービスとして「人事制度設計」サービスとして主にクライアント従業員の人事制度を構築するプロジェクトを提供していたが、その中で業績評価やKPIマネジメントについて相談を受けることが多かったため、「パフォーマンスマネジメント体系構築」サービスとして改めて打ち出すといったイメージです。
営業効率的にも一つのクライアントに複数のサービスを提供した方が良いので、周辺領域を拡張していくことはよくあります。逆にそのせいで社内で似たようなサービスが乱立して、カニバリゼーションを起こすということもあります。この業界はどこまで行っても個人商店っぽさは一定残ってしまうものなのです。
新たな概念をコンサルティングサービスに組み込む
後者については、世の中に新しい概念を浸透させていくようなイメージです。
例えばイノベーション、サスティナビリティ、SDGs、レジリエンス等、最近になってよく聞くようになったワードですが、アカデミックの世界で研究されていたものがビジネスの世界に持ち込まれて段々と浸透していったものになります。
こういったものは複数のコンサルファームが同時多発的にサービスを乱立させることも多いので、コンサルファームによって言葉の定義が異なる場合もあります。
この手の仕事の特徴としては、新しい概念を扱うので話を聞いたり議論したりするだけならとても面白いのですが、なかなかコンサルティングプロジェクトとして受注するのが難しいことです。
中には研究の段階から社外の専門家や著名人と組んで進めるというものもあります。
サービス開発のインプットとなる情報・ナレッジ整理
研究活動の分野に入るか微妙なところですが、過去のプロジェクト知見やナレッジを整理する仕事もあります。
プロジェクトの合間にやることが多いですが、プロジェクトで実施した提案や検討内容をサマライズして分かりやすくしておくことや、インデックス化・タグ付けをして検索しやすくしておくことはコンサルティングファームにとって非常に重要なことです。
クライアントから何か悩みを聞いた時に、その都度、本を読んだりリサーチをしていては非効率ですし時間もかかります。そのため、過去のプロジェクトをデータベース化しておくのです。
特にグローバルファームの場合、全世界で数十万人のコンサルタントを擁していることもあり、それぞれのコンサルタントが世界各地で似たような課題・テーマのプロジェクトをやっていることも多く、社内のデータベースを見るだけでもかなりの情報を得ることができます。
本やウェブで調べるよりもはるかにには掲載されていない、最先端の課題と解決策を知ることができるようになるのです。
こういった情報も使いながらサービス開発をしていくことも多いです。
上記に書いた通り、サービス開発や研究活動に関与すると、企業課題における様々なテーマ・領域に関与していくことになりますし、個人的にはこういった活動はとても好きでしたし、マネジャーになった今でも僕は様々な活動に関与しています。
自社組織の強化につながる組織運営活動

これは事業会社でも一般的にあると思いますが組織運営に関わる様々な活動への関与です。
コンサルファームによってはありとあらゆることに現場コンサルタントを巻き込み、様々な組織運営活動に関与することになります。
- 採用活動(面接官、各種インタビュー対応など)
- 研修・トレーニングの企画や講師としての登壇
- メンター・カウンセラー(プロジェクトと関係のない先輩・後輩の関係)
- 各種イベントの企画・運営(クリスマスパーティ、忘年会など)
こういった業務は意外と馬鹿にはできないもので、こうしたものが成功することで組織としてのケイパビリティは確実に上がっていくものです。
僕が所属しているファームではチームによって組織運営活動への関与度合いが大きく異なっていたのですが、関与が高いチームには質の高い人材が集まっていますし、コンサルティングワークのレベルも高いように感じます。
もちろんこれらの業務は義務ではなく、自ら手を挙げて関与することが多いように感じます。
その理由の1つはキャリア形成にプラスに働くことでしょう。
デメリットに挙げましたがプロジェクト型の場合、なかなかキャリア形成をコントロールしいにくい点もありますので、こういった社内業務をうまく活用してキャリアを築く方法もあります。
またコンサルには非常にパワフルで好奇心旺盛な方が多いです。
そのため、上記のような業務を純粋に楽しいと感じる方や興味があって参加する方もいます。中にはプロジェクトの合間の息抜きとしてやろうとするようなワーカホリックもいるくらいです。
組織運営に関与することでコンサルファーム内の様々なことを早く理解できるようになりますし、社内人脈も広がりますので、こういった活動への参加は個人的にはおすすめしています。
番外編としてプロボノや出向という活動もある
マーケティングや社会貢献活動的な意味合いも含まれていますが、プロボノといってNGO/NPOなどに対して、コンサルファームが無償でコンサルサービスを提供することもあります。
こちらは基本的にはプロジェクトに近い形で進める場合が多いようですが、クライアントが大企業・一流企業であることが多い一般的なプロジェクトと比べると関与者や進め方が若干異なります。
一般的なプロジェクトと比較すると、規模が小さくスピード感や手触り感もあるため、ベンチャー企業などで働いてみたいという方には面白い環境かと思います。
また営業活動の延長として位置付けられますが、クライアントに出向するという活動もあります。
大手企業でコンサルを使い慣れていて、更に年間のコンサルティング売上が大きく見込まれるところに限られますが、クライアント先に常駐して、クライアント社員と同じように仕事をするのです。
もちろんプロジェクトへの参画だけでなく、定常業務を持つようなこともあります。そういった業務の中から次の課題を見つけて、営業活動に繋げていくので、意外と重要な仕事の一つです。
僕の周りには出向している人はいないので聞いた話でしかないですが、出向先では他ファームからも何人も出向していて比較されることも多いので、パフォーマンスが安定しているマネジャークラスが出向させられているといったこともあるようです。
転職先に迷う時はプロジェクト外の業務実態を聞くのもアリ
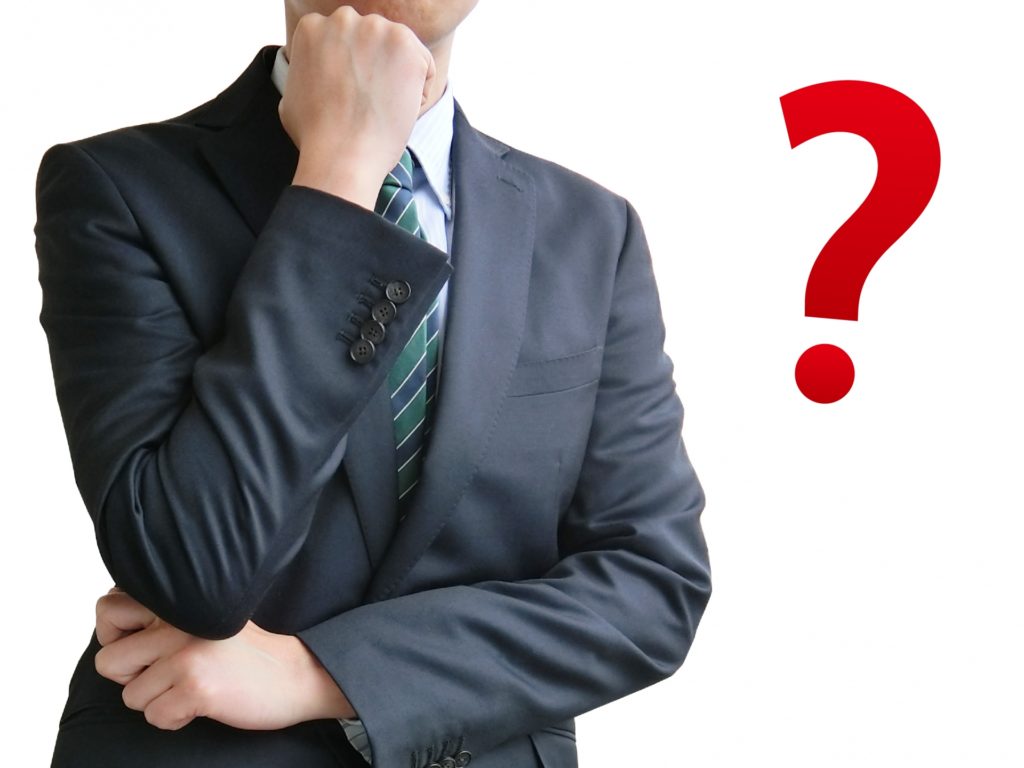
いかがでしたでしょうか。コンサルファームにおけるプロジェクト以外の仕事についてご理解いただけましたでしょうか。
実はここで記載したような内容は、個人的な好き/嫌いなどはありますが、関与することが絶対的に良い/悪いということはありません。
冒頭で述べた通り、コンサルファームの体制やスタッフに対する仕事の与え方・育成に対する考え方によって、どの程度関与することになるか大きく変わります。
そのため、複数のファームから内定が出て迷うような場合は、こういった観点で比較するのも良いかと思います。
コンサルになった後にどのように成長していくのが良いかは人それぞれ違いますし、仕事に対する価値観も各自で異なります。
僕が所属しているファームは人手不足と、育成に対する考え方から、営業活動や研究活動にはスタッフにも広く関与させていますし、 僕はその中でも特に幅広く経験している方で、それによって人脈も広がりましたし、知見を広げることができたので、結果的には良かったと思っています。
ただ、1日の時間は限られていますので、それをどのように使いたいかということを面接時にもある程度は意識しておくと良いでしょう。
また面接の中で質問する項目の一つとして、上記のような業務への関与の度合いを聞いておくと良いでしょう。

